Before/取組み前の課題
・先達から若手へ「口伝え」が中心
・職人により技法や呼称に差異
・コロナ禍で直接のコミュニケーションが減少
After/取組みによる効果
・言語の共通化が促進
・不良の過程、原因の明確化と再発防止
・継承、蓄積が会社の強みに
株式会社ヒタチの取組事例

業種
取り組みテーマ
| 富士見市で「産業の塩」と言われるネジの製造を行っている株式会社ヒタチは、創業60年を迎えた。これまでに約5,000件の注文を受け、現在は年間約300件の受注をこなしている。60年で培った技術には絶対の自信を持っているが、課題はその技術を次代の社員に継承していくこと。以前は、熟練の職人から若手にノウハウが口頭で伝授され、若手は先達の背中を見て覚えていくという形がほとんどだったが、時代と共に社員の勤続年数が短くなり、継承が難しくなってきた。また2020年からのコロナ禍で社員が分断されるという危機もあった。 | 
|
|
| 作業工程については文書化されたマニュアルもあった。だが、製造現場では手を油だらけにして作業している。作業の確認のたびに油を拭きとって紙の手順書を見るというのは煩雑だった。 コロナ禍を機に中野一宏代表取締役社長は、作業工程を撮影して動画にしておけば、理解が速いのではないかと考えた。家業を継ぐまでコンピュータ会社に勤務していた中野社長はDX導入へのハードルが低かった。さらにコロナで在宅中に、短い動画で手順を教えてくれる料理動画を見て「これすごいな」と思ったことが背中を押した。 |
||
製造工程の動画化を決定すると、まず作業分析専用ソフトを導入し、製作はすべて社内で行うことにした。技術は社外秘だからだ。だが始めてみると専用ソフトによる詳細な作業分析はさほど必要ではなく、ふだんの作業をそのまま動画に残すことが重要だとわかった。熟練工にヘッドカメラを付けて、手順を説明しながら作業してもらい、必要箇所にテロップを入れたものが中心になった。編集は汎用の動画編集ソフトで十分だった。編集は作業工程に関わりのないパート社員に頼んだ。なまじ作業を知っていると「ここは要らない」など熟練工の基準でカットしてしまう恐れがあったからだが、予想外の効果もあった(後述)。

|
||
| 完成動画は100本を超えている。すべてショート動画になっており、工程によってカテゴライズされ、詳細なインデックスが付けられている。もちろん社員が誰でも見られる。今も動画製作は続いている。
最も大きな効果は企図したとおりで、若手社員が作業行程全体を大掴みするスピードが格段に上がった。入社3年目の橋口典矢さんはこう語る。 |
||
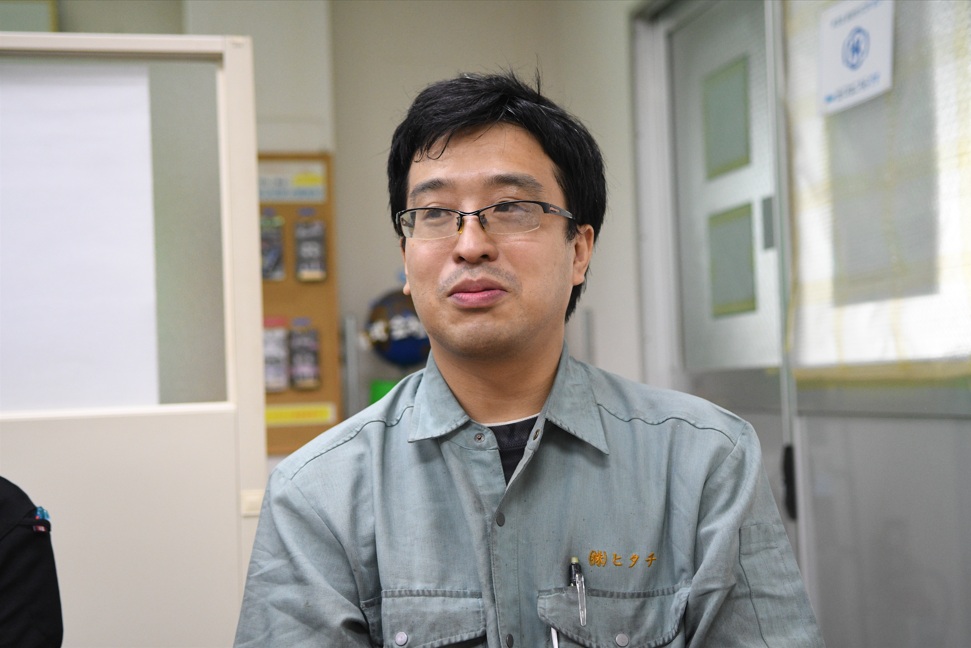  |
|
| これまであまり見ることがなかった他人のやり方を動画で見ることはできるというのは大きく変わった部分だ。それにより、意外なことに言語があまり共通化されていないことがわかった。たとえば、同じものを「フタ」と言う人もいれば「キャップ」と言う人もいるようなもの。これなどは、作業を知らない人に編集を任せたことで、明らかになったことだった。 「ナレッジが暗黙知のまま継承されていることが、形式知化することで判明したということです」(中野社長) ナレッジ=作業のノウハウや知識が職人によって差異があっても、それを統一することはしなかった。しかし、同じものを人によって違う呼び方をしていると影響が出るので、共通言語化を進めた。 熟練工側のメリットも少なくない。 勤続20年の村上勇太圧造課長によると「やっていく中で自分がいかに非効率的にやっていたか認識できた。作業中に工具がなければその都度取りに行くのは時間の無駄だとわかり、要るものを全部用意してからやるようになり、作業の効率が上がった」という。 また教える立場としても、若手が話を聞きに来ることや、呼ばれてその場に行くことが減った。 重要なことは、意図しない不良品が出てしまったときの再発防止にも動画が有効だということだ。 「書面だけで残っているより、動画でこういうふうになって不良が出ている、という方が納得も対策もしやすい」(村上課長) そして村上課長はこうも語る。 「今までこれでOKだったことにプラスアルファしていくことが自分の中では多い。それが過去の人たちにはどう映っているのかわからないが、個人的には改善されていると思う」 単なる継承ではなく、発展的継承というべきか、これこそヒタチにとって大きな財産だろう。  |
||
製造現場以外のところでの動画マニュアルもある。撮影者は中野社長自身で、それはトイレ掃除。どうやったら効率がいいかを動画で残している。窓拭きまで合わせて10分以内にできるという。
DX化とは、ツールの導入ではなく、課題を見抜き、現場に根ざした方法で解決する人間の知性の営みだ。大事なのはDX化によって企図するもの。トイレ掃除の動画もその一例だが、ヒタチのDX化が成功した背景には中野社長の中に確固とした思いがあったことが大きい。
それが「僕はナレッジをどう残すかということにすごく興味がある」という中野社長
の言葉ではっきりした。
「自分の親かそれより年上の人に口伝えで教えてもらうときに、ジェネレーションギャップがあって、うまく伝わらない。教わる方は、何を言ってるのか分からないし、職人さんの方は『あいつやる気がない』となってしまう。だから継承のために、動画システムの導入は必須だった」(中野社長)
継承。それは現在いる熟練工の技を若手に伝えるだけではない。
中野社長が前職を辞して家業を継いだのが30年前。現在は有名時計メーカーの部品製造も請け負っている。30年で会社の技術は大きく進化した。
「代が替わったときに、もう一度30年かけるのか、ということ。同じことを繰り返すのではなく、こういう動画を残しておいて、これを見ればいい。そういう継承がされないのは未来の人たちが気の毒だ。
僕は、立派な書庫に並べられた厚い背表紙の本よりも、真っ黒になるまで何度も何度も読まれるのが本当の良書だと思っている。そういうものを残したい」(中野社長)
その財産が蓄積されていることは、同業他社の中で大きな強みになり、競争力でも上回れるだろう。
ヒタチのDX化が進んだのは、中野社長が前職での経験から着地点を描くことができたからだが、それも作業のノウハウや知識を次代に継承したい、という強い思いがあったればこそだ。
「自分の仕事は、ナレッジを未来に残して卒業」という中野社長は、将来のヒタチで次世代の社員がこんな会話を交わすことを思い描いている。
「この人、センサーなくて、これ作ってるんだね、すげえな」
「この人たち、もう会社にいないけど、作業スピード、超早くね?」
こんな若者たちがいる限り、ヒタチの技術は未来に生き続ける。
株式会社ヒタチ